基準改正の背景と理由
住宅・建築物の省エネルギーは平成11年基準から平成25年基準に改正されました。
- 建物全体の省エネルギー性能をよりわかりやすく把握できる基準とするため、「一次エネルギー消費量」を指標とした建物全体の省エネルギー性能を評価する基準に改正されます。
- 外皮(外壁や窓等)の熱性能については、適切な温熱環境の確保などの観点から一定の水準(平成11年度基準相当)が引き続き求められます。
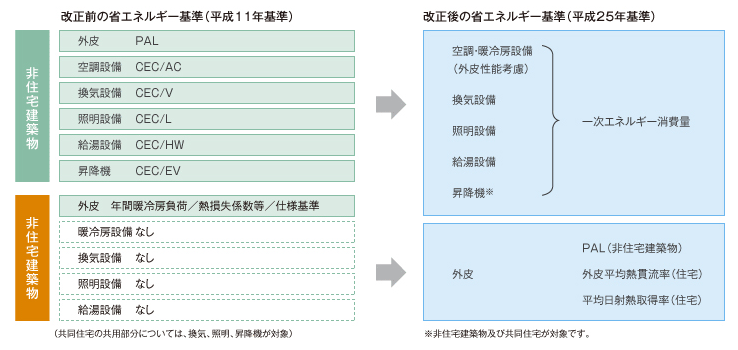
一次エネルギー消費量基準の考え方
一次エネルギー消費量とは?
化石燃料、原子力燃料、水力・太陽光など自然から得られるエネルギーを「一次エネルギー」、 これらを変換・加工して得られるエネルギー(電気、灯油、都市ガス等)を「二次エネルギー」といいます。
建築物では二次エネルギーが多く使用されており、それぞれ異なる計量単位(kWh、l、MJ等)で使用されています。
それを一次エネルギー消費量へ換算することにより、建築物の総エネルギー消費量を同じ単位(MJ、GJ)で求めることができるようになります。
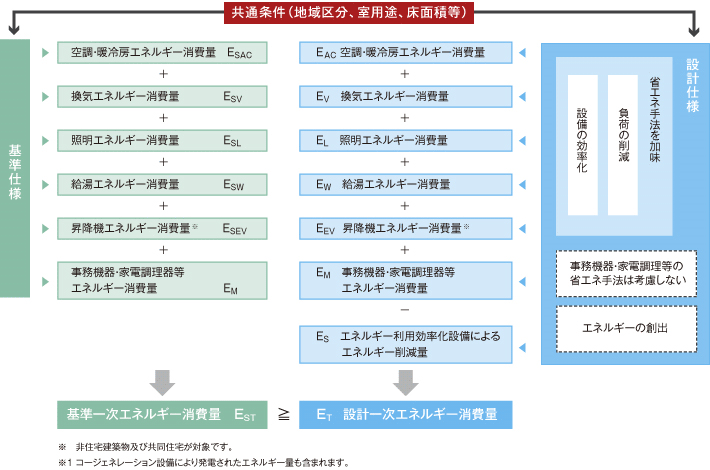
住宅の外皮
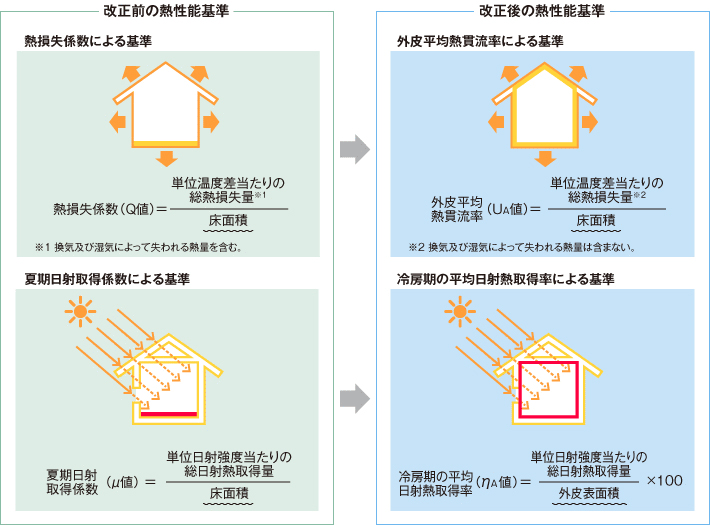
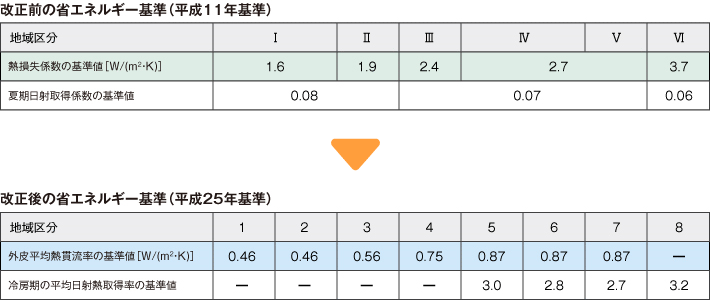
地域区分の変更
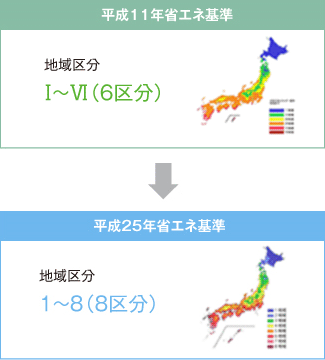
詳しくはこちらをご覧ください。
断熱厚さと省エネ基準適合検討フロー
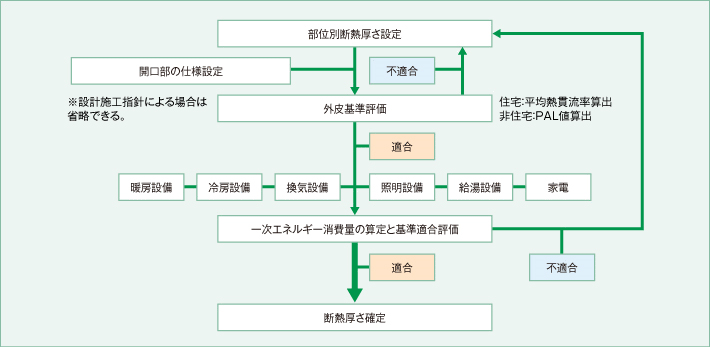
部位別断熱厚さ
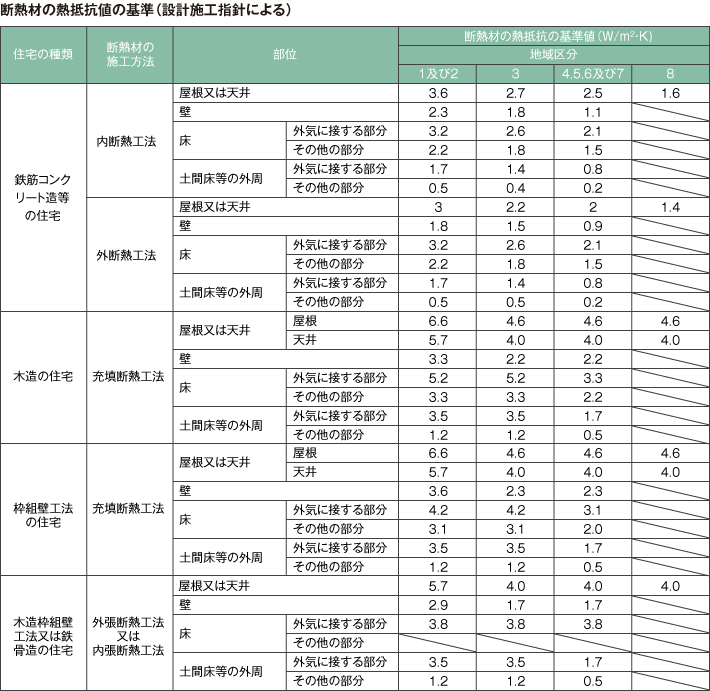
EPS断熱建材の熱伝導率(λ値)
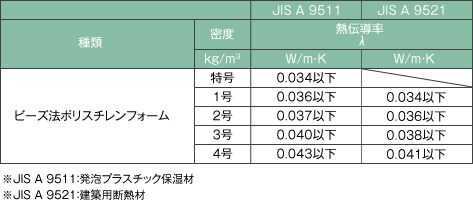
熱橋部分の断熱補強
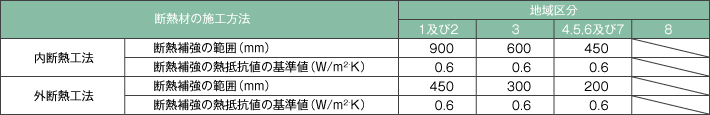
断熱材の厚み(d)の求め方
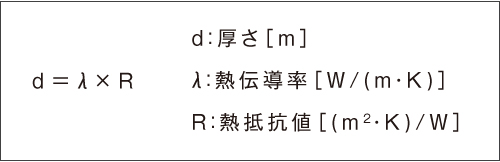
断熱材の厚みは、断熱材の熱伝導率に必要な熱抵抗値を掛けることにより求められます。
なお、計算にて算出された値はメートル単位であることに注意してください。
計算例
4地区において鉄筋コンクリート造の壁に必要なビーズ法ポリスチレンフォーム3号品(JIS A 9511)の断熱厚さを求める。
- 4地区の鉄筋コンクリート造の壁に必要な熱抵抗値は上記の表より R=1.1(W/m2・K)
- ビーズ法ポリスチレンフォーム3号品(JIS A 9511)の熱伝導率は上記の表より
λ= 0.040(w/m・K)
よって上記計算式に代入して計算すると
d = λ×R = 0.040 × 1.1 = 0.044m = 44mm となる
注意
- 上記表の熱抵抗値の基準から断熱厚さを求める際は下記の開口部比率の条件に合致していなければなりません。
- トレードオフ規定は使用できません。
- 低炭素認定基準には使用できません。
開口部比率の適用条件
| 住宅の種類 | 1地域から3地域まで | 4地域から8地域まで |
|---|---|---|
| 一戸建て | 0.11 未満 | 0.13未満 |
| 共同住宅等 | 0.09未満 | 0.08未満 |
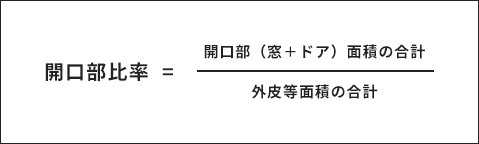
外皮等面積の合計及び開口部(窓+ドア)の面積は、本書付録3.「部位面積の算出方法」に示す方法で求められ、開口部比率は、下記の式により求める。

